
商品検索

商品検索
ようこそ、ときわオンラインショップへ!

25.03.20
こんにちは!ときわ総合サービスのおもてなし担当社員の「ときわん」です!
2024年7月から新しい紙幣が発行されましたね。
一万円札、五千円札、千円札と、全ての紙幣が新しくなるのは20年ぶりのことです。
今回は、新しい紙幣に描かれている3人の偉人たちの功績や、なぜ紙幣が新しくなったのか、旧紙幣の行方についてご紹介します。
新紙幣に採用された人物たちは、いずれも日本の近代化に大きく貢献した方々です。
豊かな日本の未来を築いた方々の物語とともに、新しいお札の世界をのぞいてみましょう。
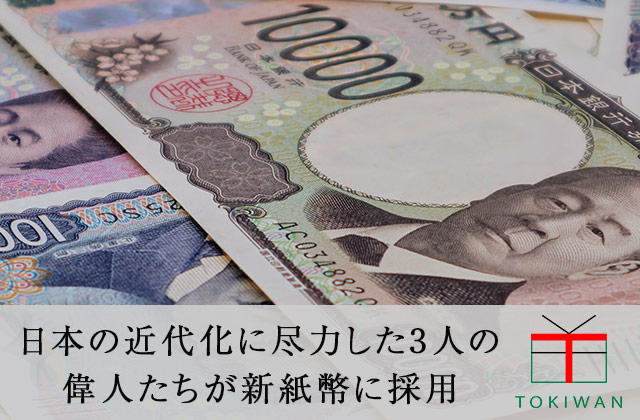
新しい紙幣に描かれることになった3人の人物は、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎です。
いずれも、日本の近代化に大きな足跡を残した方々で、その業績が評価され、紙幣の肖像に選ばれました。
それぞれの人生と功績を、時代背景とともにご紹介します。
渋沢栄一氏は「近代日本経済の父」「日本資本主義の父」などと称される実業家です。
1840年、現在の埼玉県深谷市の農家に生まれました。
27歳のとき、パリ万国博覧会の見学のため、徳川慶喜の実弟・昭武とともにヨーロッパを訪問し、先進的な経済の実情を目の当たりにします。
帰国後、30歳のときに明治政府に招かれ、大蔵省の官僚として新しい国づくりに携わることに。
その後、実業界に転じた渋沢氏は、第一国立銀行や東京証券取引所など、生涯で約500もの企業や団体の設立や経営に関わりました。
特筆すべき点は、単なる利益追求ではなく、「道徳経済合一」という考えのもと、公共の利益を重視した経営を行ったことです。
渋沢氏の講演録からまとめられた「論語と算盤(そろばん)」という有名な書籍は皆さんもご存知でしょう。
新一万円札の裏面には、東京駅の丸の内駅舎が描かれています。
この建物は、「赤レンガ駅舎」の愛称で親しまれており、渋沢氏が設立に関わったレンガ会社の製品が使用されているという縁があります。
津田梅子氏は、日本の女子教育に大きな足跡を残した教育者です。
農学者であり、江戸幕府の外国奉行支配通弁、いわゆる通訳を務めていた津田仙(せん)の娘として江戸に生まれ、岩倉使節団に同行し、わずか6歳でアメリカに留学しました。
津田氏を含めた5人の女子は、日本で最初の女子留学生です。
17歳で帰国後は華族女学校で教鞭を執り、24歳で再度渡米。
ブリンマー大学で生物学を専攻し、その研究は英国の学術雑誌に掲載されるほどの成果を上げました。
その後、1900年に女子英学塾(現在の津田塾大学)を設立し、生涯を通じて女性の高等教育と地位向上に尽力。
女性の教育こそが日本の発展につながるという強い信念を持ち、その実現に生涯を捧げました。
新五千円札の裏面には、日本の伝統と文化を象徴する藤の花が描かれ、紫を基調とした優美なデザインとなっています。
北里柴三郎氏は「近代日本医学の父」として知られる細菌学者です。
1853年、現在の熊本県阿蘇郡の庄屋に生まれ、幼少期から儒教の四書五経を学ぶなど学問に親しみました。
1871年、古城医学所兼病院(現在の熊本大学医学部)で、オランダ人軍医のマンスフェルトに師事。
医学への道を志すことになります。
1874年に東京医学校(現在の東京大学医学部)に入学。
東京医学校在学中、北里氏は「医者の使命は病気を予防することにある」と、予防医学の大切さを確信し、生涯、予防医学に尽力することを決意します。
ドイツのベルリン大学留学中の1889年に世界で初めて破傷風菌の純粋培養に成功し、その後、血清療法を確立するなど、医学の発展に大きく貢献しました。
帰国後は伝染病研究所を創設し、1894年には香港でペスト菌を発見するなど、次々と画期的な功績を残しています。
新千円札の裏面には、葛飾北斎の「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」が配されており、日本の伝統文化と近代科学の調和を表現しています。
なお、紙幣の歴代の裏面デザインについては、こちらのコラムでお伝えしています。
日本の紙幣は、最近では約20年ごとにその肖像やデザインを更新しています。
今回の刷新には、大きく分けて2つの重要な目的があります。
偽造技術が進化している中、偽造を防ぐために紙幣も改善する必要があります。
そのため、新紙幣には世界最先端の偽造防止技術が数多く採用されています。
今回特に注目すべきは、紙幣として初めて採用された3Dホログラム技術です。
お札を左右に傾けると、肖像が動いて見える精巧な仕掛けが施されており、通常のコピー機やプリンターでは再現が不可能な技術となっています。
このほかには、高精細すき入れ模様や潜在模様、マイクロ文字、特殊発光インクなど、さまざまな偽造防止技術が用いられています。
新紙幣は、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが使いやすいように改善されたデザインになっています。
具体的な改良点として、額面数字が大きくなり視認性が向上したこと、識別マークの位置が紙幣の種類によって変えられ、触って区別しやすくなったこと、色覚の個人差を考慮したカラーユニバーサルデザインを採用したことなどが挙げられます。

新紙幣が発行された後も、旧紙幣は引き続き使用できます。
店頭での支払いはもちろん、ATMでも問題なく利用可能です。
ただし、セルフレジや券売機、自動販売機など、機械によっては対応できないものも残っています。
新紙幣への切り替えは、日本銀行が市中から回収する旧紙幣を新紙幣に置き換えることで、徐々に進められていきます。
紙幣の寿命は、一万円札が4~5年程度、五千円札と千円札が1~2年程度と言われており、この寿命に応じて、日本銀行が市中から回収する旧紙幣を新紙幣に置き換えていくことで、自然に切り替えが進められるのです。
ただし、日本は家庭などに退蔵されている「タンス預金」が多いため、一万円札の完全な切り替えには時間がかかると考えられています。
因みに前回の新紙幣発行は2004年11月でしたが、9カ月後の2005年8月時点では、一万円札の切り替えは55%にとどまっていたそうです。
なお、「タンス預金の旧札は使えなくなるので交換が必要」といった詐欺には十分注意が必要です。
財布にお札を入れるときは、どのように入れていますか?
入れ方によって、金運アップが目指せるかもしれません!
ぜひ、こちらのコラムも読んでみてくださいね。
新紙幣に描かれたのは、一万円は渋沢栄一、五千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎の3人です。
それぞれ経済、教育、医学の分野で日本の近代化に貢献した偉人たちです。
新紙幣は最新の偽造防止技術とユニバーサルデザインを採用し、より安全で使いやすいものになりました。
旧紙幣は引き続き使用可能で、徐々に新紙幣に置き換わっていきます。
新紙幣の人物たちの功績を胸に、これからの時代も日本は発展を続けていくことでしょう。