
商品検索

商品検索
ようこそ、ときわオンラインショップへ!

24.04.09
こんにちは!ときわ総合サービスのおもてなし担当社員の「ときわん」です!
スーパーやコンビニなどに売られている、ほとんどの商品に貼り付けられているバーコード。
日本のバーコードはJANコードとよばれていますが、バーコードとJANコードの違いがわからないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、JANコードとは何か、バーコードとの違いなどについて解説します。
JANコードはどのように作られるか、バーコードはどのように使われるのかなどについても説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
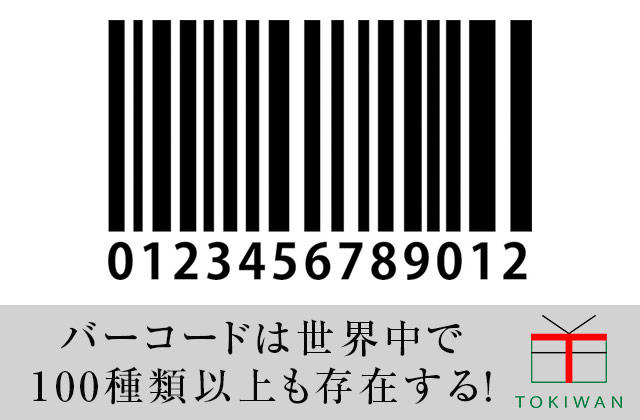
バーコードは、スーパーなどの小売店で価格チェックを正確に、かつスピーディに行うために開発されました。
バーコードの原型は、1940年代、アメリカの大学生によって開発された、太いバーと細いバーを組み合わせた多重円形のものといわれています。
その後改良が進み、1970年代には日本でも大手百貨店やスーパーなどで取り入れられるようになりました。
バーコードは、商品用途のみならず物流用途などにも使用され、世界で100種類以上もありますが、その中の1つであるJANコードについて解説していきます。
JANコードとは、「Japanese Article Number」の略で、スーパーやコンビニなどの商品についているバーコードのことです。
商品の流通コードとして商品に表示されており、JANコードをバーコードスキャナで読み取ると、企業や商品などの情報をレジに記録することができます。
なお、JANコードは日本国内での呼び方で、国際的にはEAN(European Article Number)コードと呼ばれています。
EANコードはヨーロッパをはじめさまざまな国でも使われており、国、企業、商品などの情報を読み取ることができます。
また、カナダ・アメリカで使用されているUPC(Universal Product Code)コードも存在し、EANコードと互換性がある国際的なコードとなっています。
近年普及しているQRコードは、二次元コードとも呼ばれますが、日本企業のデンソーウェーブが開発したコードです。
バーコードよりも多くの文字を識別でき、より多くの情報を記録することができる点が大きなメリットとなっています。
QRコードは、どの角度からも読み取りがしやすく、汚れや破損があっても、ある程度は読み取りが可能です。
また、専用の読み取り機器が不要でスマホやタブレットでも読み取りができるため、キャッシュレス決済に使用されるなど利便性の高さで、近年普及が進んでいます。
JANコードを使用するとどんなメリットがあるのでしょうか。
詳しくご紹介します。
スーパーやコンビニではJANコードを読み取ることにより、売上管理、在庫管理、仕入管理が行える「POSシステム」を導入しているところがほとんどです。
そのおかげで、JANコードを読み込むだけで誰でも簡単にレジ作業ができ、売上集計もすぐに行えます。
「POSシステム」を使用していると、どのような商品が、どの日の、どの曜日の、どの時間帯に売れたかという情報がわかるため、「どの商品をいつ仕入れれば良いか」といった判断がしやすくなります。
そのため、コンビニのような狭い店舗でも、こうした情報をもとに必要な分を仕入れれば良いので、在庫を管理するスペースが少なくて済みます。
また、ニーズに合わせて仕入れられるので、消費期限のあるものを無駄にすることも防げるでしょう。
売れ筋商品や客層、どんなキャンペーンをすれば売れるのかや、反対に売れない商品の情報などもリアルタイムで把握できるので、経営戦略を立てやすくなります。
先ほども触れましたが、JANコードは、EANコード、UCPコードとも互換性があるので、全世界で使用できます。
海外で商品を販売する際にも、固有の番号としてほかの商品と重複することなく使用可能です。
また、JANコードは日本の商品としての証明にもなるので、海外で商品を販売する際に日本の商品としてのブランド力を高めてくれるのもメリットです。

JANコードの作り方の前に、まずデータ構成についてまずご紹介します。
JANコードは数字のみで成り立っており、一般的に使われている13桁と、短縮タイプである8桁の2種類が存在します。
13桁タイプの構成はGS1事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットとなっています。
GS1事業者コードは、左から2~3番目までの数字が国コードとなっており、日本には450~459、490~499が国コードとして割り当てられています。そのため、日本国内で割り当てられるJANコードはどの企業でも45か49から始まっています。
なお、8桁の短縮タイプは小さな商品などに使われています。
JANコードを利用するなら、事前にGS1事業者コードの申請をしなければなりません。
インターネットか郵送で申し込む方法があり、登録料がかかります。
有効期限は3年なので、それ以降は更新が必要です。
GS1事業者コードが貸与されたら、商品ごとに商品アイテムコードを設定します。
商品アイテムコードは、その企業が自由に設定できますが、ほかのコードと重複しないように設定しなければなりません。
GS1事業者コードが9桁なら商品アイテムコードは3桁、GS1事業者コードが10桁なら商品アイテムコード2桁、というように設定します。
そして、最後の1桁のチェックデジットを計算します。
チェックデジットは、JANコードの読み取りに間違いがないかをチェックする役割があり、印刷会社やGS1Japanのホームページなどでも算出できます。
JANコードの作成を終えたら、JANコードを印刷します。
自分たちで印刷してしまうとバーコードで正しく読み取りができない場合もあるので、印刷会社に依頼するのが一般的です。
バーコードはソースマーキング、インストアマーキングという2種類の使い方があります。
それぞれ解説します。
ソースマーキングとは、製造元や販売元などが、商品の製造・出荷段階で、JANコードを商品の包装や容器などに印刷したり、貼り付けたりすることをいいます。
スーパーやコンビニ、小売店などで売られている食料品や日用品などの数多くが、ソースマーキングされています。
ソースマーキングをしたい場合は、GS1事業者コードの申請が必要です。
ソースマーキングされているJANコードの先頭2桁は、日本を表す45か49からスタートしています。
野菜や肉などの生鮮食品は、重さによって値段が異なることが多いので、スーパーなどではその店舗独自のバーコードが貼り付けられている場合があります。
これをインストアマーキングといいます。
インストアマーキングの場合、GS1事業者コードを申請する必要がありません。
データ構成は自由に設定でき、JANコードにはない価格情報もデータに盛り込むことができます。
JANコードと区別するために、先頭2桁は20〜29を使用します。
JANコードは金額が一瞬でわかるシステムで、お金とも深い関わりがありますよね。
JANコードやバーコードについて詳しく知ることができたら、次はお金についての雑学も学んでみませんか。
「明日から使えるお金の雑学!知っておくと周囲から一目置かれる小ネタ」もぜひチェックしてみてくださいね。
日本はもちろん、海外のお金の雑学も知ることができますよ。
バーコードの原型は1940年代にアメリカの学生によって開発されました。
JANコードとはバーコードの一種で、日本国内で使われています。
なお、QRコードはバーコードよりも多くの情報量を記録することが可能です。
JANコードは、売上管理・在庫管理がしやすく、消費者動向が把握でき、全世界で使用できるメリットがあります。
JANコードは主に使われている13桁タイプと8桁の短縮タイプがあります。
13桁タイプはGS1事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットを設定し、印刷して商品に貼り付けるなどの方法により使用します。
バーコードは製造元などが出荷時にJANコードを設定するソースマーキングと、スーパーなどで独自にコード設定を行うインストアマーキングの2種類があります。
お店などでよく見かけるバーコードですが、詳しい知識があると見方も変わりますよね。
普段はあまり気にしていなかったバーコードをチェックしてみるのも楽しいですよ!